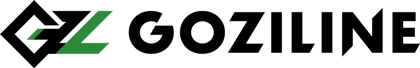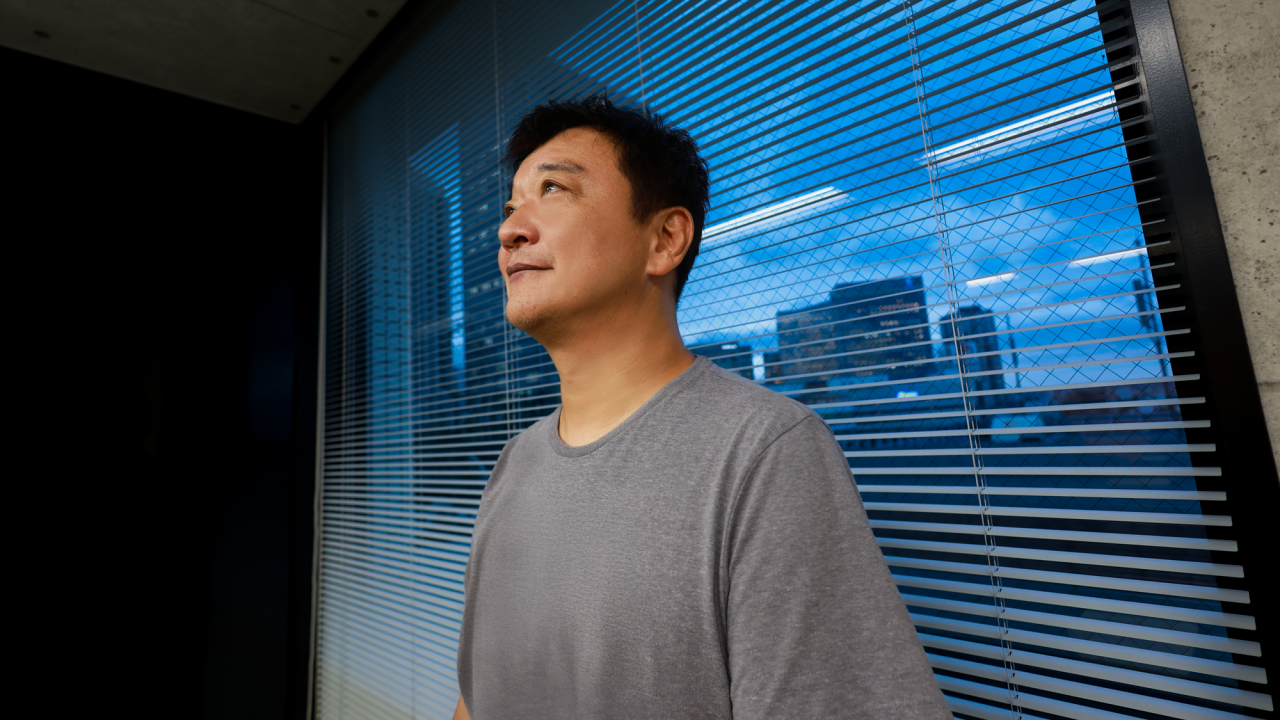ユークスという会社を皆さんはご存じだろうか。最近では『デジボク地球防衛軍』シリーズや『テイルズ オブ アライズ』などの”良ゲー”の制作に関わっている。また、プロレスゲームも長きに渡って制作しており、古くは『闘魂烈伝』シリーズなどを夢中で遊んだ方もいるだろう。2025年の8月にゲーム業界をざわつかせた「アクアプラスの子会社化」というニュースで知った方もいるかもしれない。
筆者自身、「ユークス」という会社の存在はよく知っていて、古くは『闘魂烈伝』、そして『封神領域 エルツヴァーユ』という作品を熱心に遊んだことがある。
そしてここ数年のユークスが関わっている作品は実に遊びごたえがある。IPものはしっかりとそのIPのらしさを汲み取りつつも、独自性と作り込みを感じる。
「こんなところまで作ってるのか」というような驚きがあることも多い。良作の縁の下の力持ちという印象が強いメーカーである。
10月23日に発売された『ダブルドラゴン リヴァイヴ』と『ゼンシンマシンガール』も制作をユークスが手掛けているが、どちらも尖っていて遊びごたえのある作品となっている。
『ダブルドラゴン リヴァイヴ』については歴史あるIPのらしさを残しつつも、大胆に今風の調理をした作品という印象だ。そして、一部のモードが驚くほど歯ごたえがある。
そして『ゼンシンマシンガール』のほうは、驚くほど自由な雰囲気だ。ぶちぬけたキャラクターと世界観に目が行く作品だが、ローグライトアクションとして遊びごたえがある。
2025年10月23日発売の『ダブルドラゴン』シリーズ最新作。伝統ある横スクロールアクションをベースに、今風のスタイリッシュな動きや大技を盛り込まれている。アークシステムワークスの持つ格闘ゲームのノウハウと、ユークスの作りこみが光る意欲作。
参考記事:【レビュー】格闘ゲームの要素が強めにトッピングされた『ダブルドラゴン リヴァイヴ』。挑戦を感じる新作のプレイフィールを紹介!
対応機種:PlayStation5 / PlayStation4 / Xbox Series X|S / Xbox One / STEAM / Nintendo Switch / Epic Games Store
昔からあるメーカーで、プロレスゲームを多数制作し、良作を支える「ユークス」。
でも、「ユークスってどんな会社なのだろう」、「どうしてアクアプラスを子会社化したのだろう」。
そんな疑問を持つ方は筆者だけではないはずだ。
なんとかお話を聞けないだろうかと考えていたところ、クリエイターの天河信彦先生にご紹介いただき、貴重なインタビューの機会をいただくことができた。
お話をうかがったのはユークスの代表取締役・谷口 行規 氏である。

▲ユークスの代表取締役社長の谷口氏。ユークスの歴史を知る谷口氏に、ユークス誕生秘話から、新たな挑戦までを語ってもらった。
ユークスの創業とその理念とは
――今日はインタビューを引き受けていただき、ありがとうございます。まず、ユークスという会社の成り立ちについて教えていただけますか?谷口社長は、学生の頃にフリーランスのゲームプログラマーを経て、ユークスを創業されたとお聞きしました。ゲーム作りに興味を抱いたきっかけについてお聞かせいただけますか?
谷口氏:子供時代に、ゲームセンターでインベーダーゲームを熱心に遊んでいたんです。そして、中学生の頃、「パソコンがあればゲームが作れる」ということや「パソコンがあればずっとゲームができるぞ」みたいな情報を得てしまったんですよ(笑)当時はパソコンショップがたくさんありましたね。パソコンと机と椅子が置いてあるみたいな店が多くて、朝いちばんに椅子に座ればそのまま一日パソコンを独占できるというような環境でした。わたしもパソコンショップに通い詰めて、雑誌に載っているプログラミングコードを打ちこんでいるうちにだんだんと知識がついてきました。
――当時のパソコンショップには、同じようなプログラマーの卵がたくさんいたと聞いたことがあります。そこからどのように仕事になっていくのでしょうか。
谷口氏:ゲームを仕事にしたのは16歳です。高校生の時ですね。パソコンショップの元従業員から「広島でゲーム会社を立ち上げた」ということで仕事に誘われ、そこからゲーム開発の道へ踏み込んでいくことになりました。当時はまだ未成年だったので、仕事の契約書に押印をする際は父親にお願いしていました。契約書に記載された給与金額が父の給与よりも高かったことに父がとても驚いていたのを今でも覚えています(笑)
――16歳でですか。社会に出るのが早いですね。
谷口氏:当時はゲーム開発という仕事自体がまだ新しくて、実際に働く中で学ぶことのほうが多かったですね。一方で、仕事を一人でこなしていくうちに、「いつかは自分の作りたいゲームを自社ブランドで出してみたい」という思いも芽生えてきました。大学進学をきっかけに、拠点を広島から大阪に移して業務委託契約を継続していましたが、会社が経営難に陥り別の会社との契約を模索し始めました。当時のスクウェアさんとかにもコンタクトを取りましたが、大阪にあるとあるゲーム会社から「明日からすぐ仕事をやってもらいたい」という話をいただいたんです。早く仕事をしたかったというのもあって、大阪の会社の仕事を受けることにしました。
――大阪の会社ではどのようなゲームを作られたのでしょう。
谷口氏:シューティングゲームを作りました。作っている途中のシューティングゲームだったんですが、1年以上かけて1ステージしかできていない、しかもバグだらけという状態でメインプログラマーが退職したという状況で、自分から見ると、最初から作り直したほうが完成まで早いというような状態でした。なので、そこから1カ月でステージ3面くらいまで作って、3か月後にはマスターアップしていましたね。その時の企画・プロデュース担当が天河信彦さんです。実は、ユークスの創業スタートというのは夢のない話で、外注の仕事をこなしているうちに、税理士から「お金の管理が楽になるから、早めに会社にした方がいいよ」とアドバイスを受けたのが始まりなんです(笑)そこから社名を考えました。いざ名前を決めようとしたとき、留学中のことを思い出したんです。当時、わたしの下の名前「行規(ゆきのり)」の発音が難しかったようで、友人たちからは「ユーク!」と呼ばれていました。その呼び名に、これから一緒に面白いゲームを作る仲間がどんどん増えていってほしいという願いを込めて、「ユークス」と名付けたんです。
――天河先生は古くからの友人なのですね。一人の会社だったユークスに人が増えたのはどういった経緯があったのでしょうか。
谷口氏:ユークスの創業初期は、本当に“友達の集まり”のような感じでした。振り返ると、その始まりは高校生のとき。たまたま出席番号が近くて仲の良かった友人に、「何か面白いものを一緒に作ろうぜ!」と声をかけたのがきっかけでした。それぞれの役割も、「○○は絵が上手いからキャラクターデザインを」「○○は口がうまいから営業をやってみてよ」といった感じで分担していましたね。当時は「いつかこのメンバーで会社をつくろう!」なんていう漠然とした夢もありました。大学生になって自分の会社を持てるようになり、最初は当時の友人たちに声をかけて仕事を手伝ってもらっていました。そのうちに「あの日の夢を形にしたい」という思いから、「ユークスの社員として一緒に働かないか?」と改めて誘ったんです。そこから少しずつ仲間が増え、ユークスの社員も増えていきました。ちなみに、その高校時代の友人たちは、今でも「ゼネラルマネージャー」や「営業担当」としてユークスで活躍していますよ。
――長い縁のある友人たちと今も働いておられるのですね。羨ましいです。ゲームとしては『ハーミィホッパーヘッド スクラップパニック』がユークス初の作品になるのでしょうか。
谷口氏:はい。ユークスにとって、初の受託開発によるゲーム作品となります。ソニーさんから依頼されて作った、プレイステーションの初期に発売された横スクロールアクションです。ユークスとしては、ハードの節目に作品をいち早く出せたというのは大きな経験になりました。プレイステーションを見たときに、「これからは3Dの時代が来るな」と強く感じましたし、その分、開発費も上がっていくだろうなと思っていました。
1995年9月29日にSCEから発売された プレイステーション用ソフト。初期のプレイステーションでは珍しい横スクロールアクションとなっている。ステージ道中で集めた「タマゴ」に「スター」を与えると、「タマゴ」がオトモとして活躍するシステムを盛り込んでいる。70ステージが用意されており、見た目からは想像できないほど歯ごたえのある難度になっている。

▲画面は『ハーミィホッパーヘッド スクラップパニック』より。
闘魂烈伝が最初の柱になる
――この時代のユークスといえばやはり『闘魂烈伝』シリーズかと思います。この作品はどのような経緯で作ることになったのでしょう。プロレスが特別に好きだったのでしょうか?
谷口氏:実は、プロレスそのものよりも「プロレスゲーム」が大好きだったんです。相手を倒したときの喜びや負けたときの悔しさ、技がバシッと決まったときの爽快感。試合の組み立て次第で攻略も変わる、そんな奥深さがあって、本当に面白かったんですよ。昼休みに会社で対戦して、負けた人が買い出しに行く、なんてことを毎日のようにやってましたね(笑)そんなことをやっているうちに、3Dの時代がやってきました。「じゃあ、うちは3D化で飛躍的に上がる表現力を使って3Dで何を作るのか」と考えたときに、“人の感情をより揺さぶるものを作りたい”というテーマが自分の中で決まっていて、「感情を揺さぶるものといえば、やっぱり“人”だよな」と思いました。それで、普段遊んでいたプロレスゲームを3Dにしたらどうだろう、と考えたのが始まりです。以来、ユークスは“人”をリアルに描き、動かすことにこだわり続けています。
――『闘魂烈伝』を遊んだとき、ボイスに驚いたんですよね。キャラクターのものではなくて、レフェリーや観客 のボイスにもまさしく「人」を感じました。
谷口氏:プロレスの戦いだけではなくて、会場の雰囲気を含めて盛り込もうとしていました。実際のプロレスの試合って、はじまるまでが長いじゃないですか。ユークスのプロレスゲームはバトル以外の部分もかなり尺をとっていますね。
1995年に発売されたプレイステーション用ソフト。ユークスが制作し、トミーが発売を手掛けたプロレスゲーム。新日本プロレスリングを題材としたことで、プロレスファンが夢見るドリームマッチを「戦い」として楽しめるゲームとなった。「打つ・投げる・極める」の3要素をゲームの中で「三すくみ」に落とし込んだことで熱いかけひきがかんたん操作で楽しめるのも特徴。しっかりと響くボイスやキレのあるサウンドなど演出面の作りこみにより臨場感も高い。発売と同時に人気を博し、シリーズ化も行われた。

▲画面は『新日本プロレスリング 闘魂烈伝』より。
――制作時のエピソードで、印象的なものがあればお聞かせください。
谷口氏:モーション制作では、グラフィッカーが技の動きを“目コピ”で再現していたんですよ。映像資料や実際の試合映像を、VHSのテープが擦り切れるほど繰り返し見て観察しながら制作していました。実は、『闘魂烈伝』の技モーションは、先ほど話に出た私の高校時代の友人も作っていて、まだ世に出ていない動きを試行錯誤しながら作り上げていく過程も熱心で、それが実際に実装されたときには、ものすごく喜んでいたのを今でも覚えています。
――『闘魂烈伝』の手ごたえはいかがでしたか?
谷口氏:最初の時点で30万本ほど売れ、シリーズ化も早い段階で決まりました。「面白いものができたな」という手ごたえはありましたし、それが結果につながったのは本当にうれしかったですね。日本で初めてプロレス表現に特化した会社としての自負も芽生え、以降はプロレスゲームを会社の柱に据えるようになりました。
はじめての自社IP『封神領域 エルツヴァーユ』の話
――『闘魂烈伝』の合間、『封神領域 エルツヴァーユ』という自社パブリッシング作品を発売されています。実はわたし、こちらの作品がだいぶ好きでして……。なにかエピソードがあればお聞かせください。
谷口氏:事前にいただいたインタビューの質問状に『エルツヴァーユ』の文字があって、正直びっくりしました(笑)『エルツヴァーユ』は、受託案件を重ねて勢いがついてきた頃に、「自社IPへの挑戦」として制作した作品なんです。当時の市場を見て、10万本売れれば採算が取れるだろうという試算を立てていました。ところが、ふたを開けてみたら驚くほど売れなくて……。ありきたりな言い方ですが、本当に真っ青になりましたね(笑)ただ、フランスの会社が協力して海外で販売してくれたおかげで、なんとか持ち直すことができました。もしそれがなかったら、大変なことになっていたと思います。
――オープニングはアニメーションを使っていたり、今思うとリッチですよね。
谷口氏:はじめての自社IPですからね(笑)力も入るわけです。
1999年に発売された初代プレイステーション用ソフト。シンプルな操作で遊べる3D格闘ゲーム。多次元に同時に存在する生命体「イハドゥルカ」を目指し、多次元のキャラクターたちがバトルを繰り広げる。世界観やキャラクター、物語の作りこみを感じる一作。かけひきのルールを理解すれば対戦もアツい作品。
――僕が最初に遊んだのは、おもちゃ屋で見かけたからなんですよね。格闘ゲームならなんでも遊んでいた時期だったんです。でも、格闘ゲームというだけでなく、描きこまれたキャラクターや物語、演出なんかに驚いたんですよね。「手のこんだゲームだな」と子供心に思ったのかもしれません。
谷口氏:当時の開発者は今もユークスで働いているので、この話を聞いたらきっと喜ぶと思います。『エルツヴァーユ』は、確かに売り上げは振るいませんでしたが、当時の会社としてやりたいことが詰まった作品ですね。自社IPに挑戦するにあたって、社内の精鋭チームを作りました。ユークスは当時から自主性を大切にしていて、『エルツヴァーユ』にしても、出てきたアイデアや作り込みを頭ごなしに否定するようなことはしなかったんです。だからこそ、あんな不思議で個性的なゲームが生まれたのかもしれませんね。
――谷口社長は、『エルツヴァーユ』にどのような形で関わったのでしょう。
谷口氏:出てくるアイディアや仕様に「いいじゃん!」という所感を伝えたりしたほか、プログラマーとしても関わりました。CPU戦を担当したんですが、ここは好きなことをやらせてもらいましたね。当時の格闘ゲームのCPU戦というと「パターン化」して攻略される傾向があったんですが、『エルツヴァーユ』では、CPUがプレイヤーの行動を学習していって、次にどの技を出すか予測してワンパターンでは勝たせないような作りにしたんです。飽きずに長く遊んでもらいたいという気持ちからですね。
――この時代のユークスは、今から見ても明らかに尖っているように見えます。『エルツヴァーユ』も頗る尖ったゲームですが、スクウェアからリリースされた『双界儀』なんかも、世界観とキャラクターにゴリゴリにこだわったゲームかつ、唯一無二のプレイフィールがあるゲームですよね。
谷口氏:『双界儀』は、スクウェアさんが開発会社を集めてコンペみたいなことをやっていた時代の作品なんですよ。いろんな会社から新作の企画を募って、その中で気に入ってもらえたものに予算をつけて実際に作らせてもらえるんです。そこで気に入ってもらってスタートした企画でした。当時遊んでくれた一部のユーザーさんには強く刺さったみたいで、今でも覚えてもらえてるのは本当にうれしいですね。
WWEを題材にしたゲーム制作へ
――2000年代、日本のプロレスを題材にした『闘魂烈伝』ではなく、WWEをテーマにしたゲームをリリースするようになっています。この経緯についてもお聞かせください。
谷口氏:ドリームキャスト時代の『闘魂烈伝』の開発費を試算したときに3億円くらいかかることがわかりました。当時の感覚で、ここまで開発費があがってくると、国内中心のプロレスゲームでは商品として成り立たないだろうと感じました。続けたい思いもありますし、ファンの声も聞こえていましたが、会社が続いていかなければ作品を世に出すこともできません。そこで、市場規模の大きいWWEのゲームを作ることにしました。ここで作風もガラリと変わって、カジュアルにプロレスゲームとして作っていた『闘魂烈伝』から、ディープなファンを狙った作りになっていきます。ストーリー寄りのものになっていったのもこの頃ですね。
『WWF SmackDown!』として海外で発売したソフトを日本向けにローカライズした作品。2000年発売で、日本国内では『エキプロ』として知られる。WWEを題材にした作品で、実写映像を盛り込んだダイナミックな登場シーンなどが人気を博した。以降、海外ではシリーズ化され、2018年発売の『WWE 2K19』まで開発を手掛けている。

▲画面は『エキサイティングプロレス』より。
――WWEのゲームはその後、長い間に渡ってリリースされていますよね。
谷口氏:ファンの数が違うというのがまず大きいですよね。プロレスやWWEそのものに盛り上がってもらうことでユークスのゲームが売れるという流れもあるので、興行そのものの人気アップに協力するということを始めました。ゲーム会社として少し特殊な歩みをしはじめたのはWWEのゲームを作り始めてからですかね。WWEの作品を18年連続で毎年リリースしたことがギネス記録にも認定されたんですよ。
――2006年には、再び新日を題材にし、国内複数団体が登場する、 『レッスルキングダム』が発売されました。
谷口氏:『闘魂烈伝』が終わったあとも新日さんとの関係は続いていて、実は2005年にユークスが新日を子会社化したんですよ。レッスルキングダムの発売を目前にして新日さんのほうから「会社の継続が難しい」と相談を受けて、救済しないわけにはいかないなと思いました。ユークスは、長年プロレスゲームを作らせてもらったことで成長できた会社ですからね。少しでも力になれたのは、本当にうれしかったです。
――架空の女子プロを題材にした『ランブルローズ』も楽しく遊ばせていただきました。
谷口氏:コレは、コナミさんからお声がけいただいた案件ですね。ちょうどユークスとしても、男らしいタイトルばかりを作っていると少しマンネリを感じていた時期で、「もう少し違う方向性の作品にも挑戦してみよう」という思いがありました。そこから女子プロレスをテーマにした企画の話が持ち上がり、「架空の女子プロ的なドラマを作ろう」ということで話がまとまりました。新しい表現へのチャレンジということもあり、現場はとても活気があったようです(笑)
2005年にコナミから発売された女子プロレスを題材にしたゲーム。架空のプロレス団体「ランブルローズ」で繰り広げられるドラマを描く。登場キャラクターたちの戦いに至るまでのドラマをしっかりと描き、そのうえ個性ある動きで熱い試合を楽しめるという秀作。2006年には、Xbox360で『ランブルローズXX』が発売された。

▲画面は『ランブルローズ』より。
ユークスの上場とその後
――2001年にはユークスは上場しています。上場のビジョンはどの時期からあったのでしょうか。
谷口氏:仲間が集まりはじめて間もない頃には「いずれ上場するぞ」と話していましたね。当時は初代プレイステーションの時代で、ゲーム開発の費用が今後どんどん上がっていくだろうと予想していました。上場すれば資金を調達しやすくなるのでは、という見通しがあったんです。ただ、実際はそんなに甘くはなくて。上場すると、会社として利益を出し続けるという責務が生じます。ゲームは発売してみないと売れるかどうかわからないビジネスですから、「エンタメを主な生業にする」というのは本当に大変だと、2001年に上場してあらためて実感しました。
――上場後、会社に変化はありましたか?
谷口氏:規模は大きくなりましたが、あんまり変わっていないという印象です。プロレスゲームを作りながら、受託案件 をこなしているというのが長く続いていましたしね。
――現在、ユークスはゲームのほか、遊技機、XR、MR、ARなどを手掛けていらっしゃいますよね?こうした多彩な展開を行うようになった経緯についてはいかがでしょうか。
谷口氏:一見すると多彩な取り組みに見えるかもしれませんが、その多くはゲーム開発で培ってきた技術やノウハウの“応用”なんです。ユークスは創業以来、ゲームづくりを通して「仕組みをつくる力」を磨いてきました。仕組みをつくることで、開発効率を高めたり、新しい表現方法を生み出したりと、さまざまな可能性が広がります。その考え方は遊技機やXR、MR、ARといった領域にも通じています。多様な事業展開は“新しいことをやった”というより、長年積み重ねてきた技術と仕組みづくりを、より広い分野へ自然に拡張していった結果なんです。これからも、ゲーム開発で培った強みを基盤に、幅広い領域で価値を提供していきたいと思っています。
▲プロデューサーを内田明里氏が務めた「AR Performers」はユークスによるアーティストプロジェクト。2015年から2022年まで活動した。完全生ライブを特徴とした当時にして斬新なプロジェクトだった。
――上場後、ユークスという会社に変化はありましたか?
谷口氏:上場を経て事業規模は確かに大きくなりましたが、ユークスの本質は大きく変わっていないと感じています。プロレスゲームをはじめ、受託案件 でも常に“良いものをつくる”という姿勢を大切にしてきましたし、その精神は上場後も一貫しています。むしろ、上場したことで責任感がより明確になり、品質へのこだわりや開発プロセスの透明性を高めながら、多くのパートナーと安定的に仕事ができる体制が整いました。規模は大きくなっても、ものづくりへの思いと開発スタンスは変わらない、それがユークスらしさだと思っています。
脱線して「レーサー」時代の話を聞いてみる
――ゲームの話からは少し脱線するかもしれませんが、谷口社長はレーサーとしても活動しておられましたよね?どういった経緯でドライバーになったのでしょう。
谷口氏:きっかけは実はゲームなんですよ。90年代終盤にレースゲームを作ることになって、サーキットを借りて車の音を録音する手配をしたんです。そのときに、自分の車をプロドライバーに運転してもらったら、「同じマシンでもこれだけ差が出せるのか」と驚きました。すぐそこにカーブがあるのになかなかブレーキを踏まないんですよ。その後、中古のレーシングカーを安く買い、サーキットで走るようになりました。何回か走った後にプロドライバーがアドバイスに来てくれて……。ここが大きな人生の転機になりました(笑)ラップタイムがプロドライバーとあまり変わらない状態だったんです。「これはレースをやったほうがいい」と言われて、レースの世界に不思議な形で飛び込みました。はじめて5年目で全日本選手権に優勝でき、ここで一区切りかなと思ったら、世界選手権への参加をすすめられ、2年後に日本人初の優勝を果たすことができました。
2005年発売。D1グランプリ会場やD1マシンの再現にこだわり、「ドリフト」の爽快感をゲーム化することに務めたレースゲーム。D1グランプリの実況陣が、プレイにあわせた実況でゲームを盛り上げるという仕様も盛り込まれた。

▲画面は『D1グランプリ』より。
――レーサーとして異色の経歴じゃないですか。もうちょっと脱線していいですか?
谷口氏:いいですよ(笑)
――ゲーム会社の社長がレースをやることを勧められるというのはなかなかないことだと思うのですが。速く走るコツをつかむまでは早かったのでしょうか。
谷口氏:どうなんでしょう。まず、ちょっと向いているということはあっても、すごく才能があるというわけではないと思います。ただ、分析することは怠らなかったんですよ。自分と他の人の走りを比べてみて、どこが違うのか、自分はどこを変えれば他の人のように速くなるのかということを常に探っていました。もうひとつは、周囲の環境に恵まれましたね。日本のトップドライバー達とチームを組んで走れる機会が多かったんです。
――世界選手権で優勝したときは、どのような感覚でしたか。
谷口氏:ゴールした瞬間に、これはもう同じことはできないだろうなと思いました。「ゾーンに入る」という言葉が、まさにこういうことかという体験があったんです。私が優勝した世界選手権は雨のレースだったので、ブレーキの勝負になると思っていました。各国のチャンピオンや元F1ドライバーたちよりも遅らせてブレーキを踏まないと勝てないなと。日本開催の世界選手権に参戦するということで、数か月前からインタビューやテレビ出演の依頼等もたくさんあって、メディアで色々しゃべっているうちに、これで恥ずかしいレースはできないなという気持ちが高まっていって、自分でも経験したことがないような集中力が高まった状態でレースに挑みました。結果的に1レース200回くらいのブレーキングのほとんど全てを完璧に成功させて優勝することができました。後で思い出すとスローモーションに見えていたような気がします。
――レースの経験は、谷口社長にどのような影響を与えましたか。
谷口氏:まず、レースを通じて「緊張」というものに動じなくなりました。自信と集中力で緊張感をマネージメントするっていうか。また、先輩やライバルとの関係の築き方についても、多くの学びがありましたね。ゲーム業界に入ったばかりの頃は、正直、近づきにくい趣味嗜好の人もいましたが、そういった人が優れたクリエイターであることも多いんですよね。
そんな人の凄いところを見て敬意をもって接することができれば、心を開いてくれて色々なことを教えてくれるようになったという経験が数多くあったんです。レースの世界では、この経験をもとに、周囲の人の良いところだけを見るよう意識していたんです。見つけた良さや強みを「尊敬できる部分」として意識して、その人を好きになろうとしたんですよ。そうすると「合わないな」と思う人との間にも人間関係ができてきました。いろいろなことを教えてくれるし、気にかけてくれるということがわかりました。レースではみんながライバルですから、そこで「教える」なんて、なかなかできることじゃないですよね。人の力をどう借りるか、本当の意味でどう信頼関係を築くか、尊敬するかというようなこと再認識しましたね。私が座右の銘としている「他力本願」はこの辺のことを指しています。
アクアプラス子会社化
今後のユークスの歩みについて
――時間も少なくなってきましたが、アクアプラスの子会社化の話、聞いちゃっていいですか?
谷口氏:まだ合流したばかりで、具体的な計画などはこれからですが、お話できる範囲なら構いませんよ。
――8月4日に、ユークスがアクアプラスを子会社にしたというニュースが出ました。アクションゲームに長けたユークスさんが、美少女ゲームやストーリーに定評のあるアクアプラスさんと組むというのが正直以外でした。どういった経緯で、子会社に迎えることを決断されたのでしょうか。
谷口氏:まず、M&Aで企業を拡大していくというのは選択肢としていつもありました。いくつか仲介業者の方がいて、年間20件くらい案件が来るんですよ。でも、開発会社を買うと、その分仕事をとってこなくちゃいけないですし、なにより会社の規模が大きくなっても同じ仕事をやっていくだけという可能性が高いですよね。なので、足りている部分を足すのではなくて、足りない部分を補完しあえるようなところ、もしくは新しいものを持ち込んでくれるところがいいなと思っていました。そんなことを考えていた時期に、アクアプラスの話が出てきたんです。アクアプラスの親会社が売却先を探しているというお話をいただきました。当然ニュースにもなっていましたので、いくつかの企業が名乗りを上げていましたが、その中でユークスが独占交渉権をいただくことができました。アクアプラス側にも、私たちの姿勢や考え方に共鳴する部分があったのではないかと思っています。

▲今年発売された『To Heart』のリメイク版。3DCGでキャラクターを描き直した良リメイクとなっている。
――アクアプラスは谷口社長から見てどのような会社ですか?
谷口氏:アクアプラスは、まず何より“強いIPを持つ会社”という印象があります。長年にわたり、シナリオやキャラクター表現にこだわった作品を丁寧に作り続けてこられた企業で、そのクリエイティブの強さには大きな魅力を感じています。一方で、3D表現の分野では模索されている部分もあったように見受けられ、そこでユークスが持つ技術がお互いにとって良い形で作用するのではないかと考えました。ユークスは長くゲーム開発を続けてきましたが、自社IPについては『エルツヴァーユ』以降あまり積極的に展開してきませんでした。だからこそ、アクアプラスを迎えることで、新しいIPを生み出し、育てていくことにあらためて挑戦できると感じています。お互いの強みを掛け合わせることで、ユークスとしても、これまでにない価値を提供できるのではないかと期待しています。
――社長、ここで『エルツヴァーユ』が出てくると僕は感動してしまいます(笑)リップサービスでも、今日『エルツヴァーユ』の話を聞いてよかったです。
谷口氏:ユークスは『エルツヴァーユ』以降、さまざまな作品のIPをお預かりし、“魅力的なゲームとして昇華すること”に力を注いできました。ありがたいことに、近年はその取り組みを高く評価していただく機会も増えています。そうした積み重ねがあるからこそ、次は私たち自身のIPにも本格的に挑戦すべき時期だと感じています。ゲーム発のIPを、アニメや漫画、グッズなどへと幅広くメディアミックス展開していく、そんなチャレンジをユークスとしてぜひ実現したいですね。
――自社IPに力を入れていくのですね。
谷口氏:アクアプラスのIPに取り組むことはもちろん、ユークス自身がオリジナルタイトルを手がける意識も、これからしっかり育てていきたいと考えています。確かにチャレンジではありますが、今はまさに“自ら価値を生み出していく時代”だと思うんです。最近のゲーム開発費は、過去と比べものにならないほど高騰しています。大規模な案件を受けるためには、企業としての体力も求められますし、一方で受託案件が以前のように安定して出てくる時代でもありません。プロジェクトが順調にスタートしても、突然打ち切りになることも珍しくない。海外資本のプロジェクトでも同じ状況です。私はこれまで、多くのスタジオが姿を消していくのを目の当たりにしてきました。だからこそ、“受けるだけのビジネスモデル”では、いつ破綻してもおかしくないという危機感を持っています。最終的に信頼できるのは、やはり作品を楽しんでくださるエンドユーザーの皆さんです。その思いもあって、今回のインタビューを含め、ユークス自身の発信をこれからさらに強めていきたいと考えています。
――アクアプラスは、ユークスの会社になったことで、どのような変化があるのでしょうか。
谷口氏:アクアプラスというブランドの持ち味は変わらないと思います。特に、わたしも、ユークスも「こうするべきである」みたいなことを言うような性質ではないんです。新入社員の募集をするときには、「クリエイターとして挑戦できる会社」みたいなことを謳っているんですが、これに嘘はないです。だからこそ『ゼンシンマシンガール』みたいな振り切ったものもできてきます。なので、ユークスと一緒になったアクアプラスは「できることが増える」と考えています。
――楽しみにしております!!!!ユークス最新開発タイトル『ゼンシンマシンガール』と『ダブルドラゴン リヴァイヴ』が、発売されましたが手応えはいかがでしょうか?
谷口氏:どちらの作品も、レビュー記事やエンドユーザーの皆さまから高い評価をいただき、大変うれしく思っています。『ゼンシンマシンガール』は見てのとおり、ユークスの「好きなこと」「面白いこと」を全力で詰め込んだ作品です。本作は、株式会社ディースリー・パブリッシャーの岡島プロデューサーが、ユークスのクリエイターたちの開発に対する熱意を高く評価し、10年来温めてこられたアイデアを託してくださったことで生まれたタイトルです。アクションの爽快感はもちろん、クリエイターが仕込んだ細かな遊びやこだわりが物語や世界観にも随所に反映されているので、そうした点にも注目していただけるとうれしいですね。「そんなところまで作るの?」という要素も多いので、ぜひ隅々まで遊んでいただきたい作品です。『ダブルドラゴン リヴァイヴ』については、歴史あるIPでありながら、大胆なアレンジに挑戦した点が特徴です。懐かしさをそのまま再現するのではなく、今のプレイヤーや若い世代にも楽しんでいただけるように、攻撃の連携や打撃感、演出など細部までこだわって制作したベルトスクロールアクションに仕上がっていると思います。
――どちらも、「こんなところまで作らなくていいでしょう」みたいな要素がちらほら出ていて楽しい作品でした。
谷口氏:実は、ユークスの創業当初から「こだわりのユークス」という言葉をモットーに、数多くの開発に携わってきました。品質の高さはもちろん、“あっ”と驚くような面白いものを生み出すことにも、ずっと力を注いできたんです。「ここまで作らなくてもいい」という部分こそ、まさに私たちの“こだわり”の表れですね。作っていると、そうした発想や工夫はいくらでも湧いてくるものなんです。わたしは今、直接現場に立つことはありませんが、そうした“ものづくりの精神”は確実に受け継がれていると思います。
――今日はお忙しい中、ありがとうございました!

2025年10月23日発売。全身を機械化した「マシンガール」がブラック企業に乗り込んで破壊の限りを尽くす、“撃ちまくり&斬りまくり”の爽快アクション。ディースリー・パブリッシャーの代表作である『お姉チャンバラ』と『地球防衛軍』を融合させたかのような爽快なプレイフィールを持つ作品に仕上がっているそう。
プラットフォーム:Nintendo Switch2 / PlayStation5 / Steam / Epic Games Store
初対面の谷口社長からは、飄々とした印象を受けたが、お話を聞いているうちにその印象は大きく変わっていった。
ゲーム制作、経営、そしてレースにいたるまで、課題を見つけることと、課題解決までのスピードが圧倒的に速いのだ。
課題解決のプロセスはさまざまだが、時に大胆な決断を伴う出来事なども多く語っていただき、インタビューの時間はあっという間に過ぎてしまった。
インタビューを通じて、ユークスのことが少しだけわかってきた。
よくわかったというには時間も足りず、ユークスの歴史は長く、谷口社長の考えも計り知れない。
しかし、ポジティブな未来を想像できる時間だったことは確かだ。
ゲーム業界に飛び込み、技術で道を切り開いてきたユークスは、いま新しいチャレンジをしようとしている。
この先、アクアプラスと何をやっていくかはまだ明かされなかったが、未来について心配する必要はなさそうだった。補完し合うユークスとアクアプラスが描く未来については、近い将来語る機会があるとのこと。ユークスとアクアプラスの「新章」に期待したい。
記事制作Goziline、カメラマン 遠山めぐこ(https://x.com/Fuze_Meg)
goziline
様々なジャンルのゲームを大人気なく遊びます。
最新記事 by goziline (全て見る)
- 「ユークス」誕生秘話から新たな挑戦まで。谷口社長が闘魂烈伝、エルツヴァーユ、レースゲーム、そしてアクアプラス子会社化を語る【インタビュー】 - 2025年12月8日
- 【餓狼伝説CotW】12月9日配信!Mr.BIGのグレイトな動きと見どころをご紹介! - 2025年12月5日
- 【餓狼伝説CotW】『ストリートファイター』から参戦する春麗はいろいろな“らしさ”の詰まった良キャラの予感 - 2025年11月2日